退職後、すぐにフリーランスとして働く予定だけど――
「失業手当ってもらえるの?」「開業準備を進めていいの?」
そう悩むのは、まったく自然なことです。
制度の仕組みがわかりにくく、ネットの情報も断片的。
一歩間違えると、「手当が止まった」「不正受給になった」なんて話も耳にします。
でも安心してください。
フリーランスとして準備を進めながら、正しく制度を活用することは可能です。
この記事では、フリーランス薬剤師として独立を目指す方に向けて――
- ✅ 失業手当の基本と、受給できる条件
- ✅ ハローワークでの伝え方と手続きの流れ
- ✅ 受給中にできること・やってはいけないこと
- ✅ 開業と両立させるための制度の使い分け(再就職手当・受給期間延長)
など、初年度に知っておきたいポイントをわかりやすく整理しています。
「準備を進めたいけど不安…」という方も、
制度のルールを理解すれば、焦らずスムーズに独立まで進むことができます。
失業手当はもらえる?フリーランス準備中でもOK?
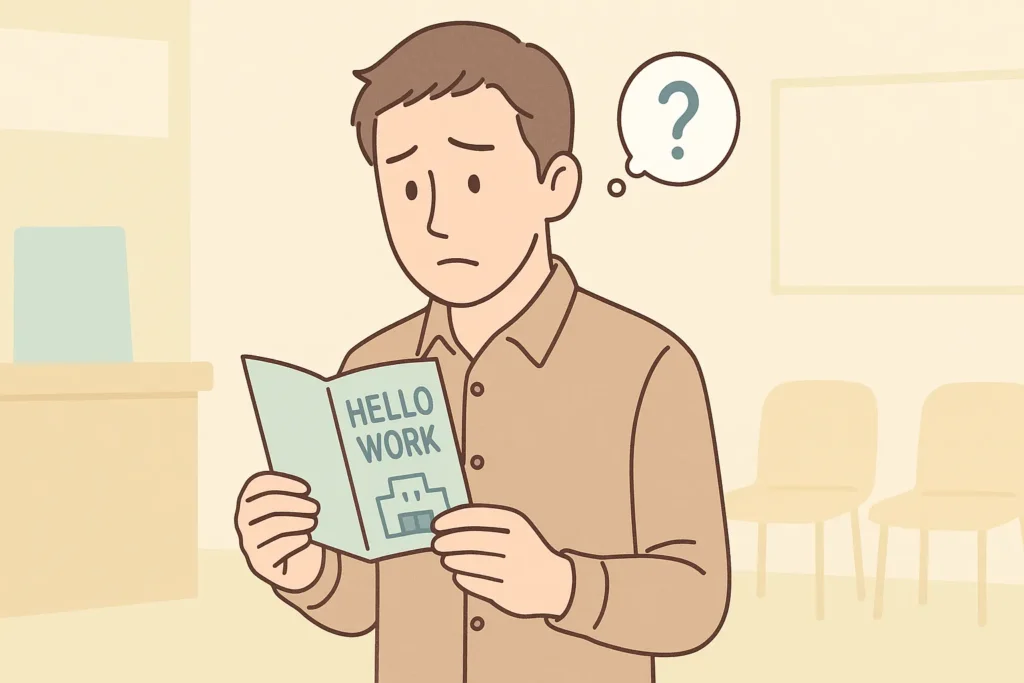
まずは、失業手当がどんな制度なのか。そして、フリーランスを目指す場合にも本当に受給できるのか。基本的な仕組みを確認しておきましょう。
この記事で扱う「失業手当」は、雇用保険制度における「基本手当(求職者給付の一部)」を指します。 わかりやすさを優先し、本記事では「失業手当」という表現を使用しています。
失業手当の制度とフリーランスへの適用
失業手当は、働く意思と能力があるのに職に就けない人に対して支給される制度です。 ハローワークに求職申込みを行い、一定の条件を満たすことで受給が認められます。
フリーランス薬剤師として独立を目指している場合でも、 すぐに開業せず、準備段階にとどまっていれば、受給対象と判断される可能性があります。
実際には、「開業準備中であり、条件に合う求人があれば就職も検討している」といった状態で ハローワークから受給が認められる例も少なくありません。
ただし、退職しただけでは自動的に受給できるわけではありません。 就職の意思があること、そして継続的に求職活動を行っていることが前提条件です。
制度改正による変更点(2025年4月〜)
2025年4月の法改正により、自己都合退職に関する給付制限が緩和されました。
- 従来: 7日間の待機期間+2か月の給付制限
- 改正後: 7日間の待機期間+1か月の給付制限
さらに、条件を満たせば給付制限そのものが免除されるケースもあります。 以下のような教育訓練や支援制度を利用している場合、待機期間終了後すぐに受給を開始できる可能性があります:
- 厚生労働省指定の教育訓練講座を受講している
- ハローワーク主催の職業訓練やセミナーに参加している
- 求職者支援制度の講座、就職支援のオンライン講座などを利用している
💡 IT・会計・営業などのスキル向上を目的とした講座であれば、 フリーランスとしての独立を目指す人も対象になる場合があります。
制度を正しく理解し、準備や伝え方を工夫すれば、 開業前の準備中でも失業手当を活用することは十分に可能です。
受給できるかの3つの条件をチェック

失業手当を受け取れるかどうかは、「保険加入期間」「求職姿勢」「働き方」の3点で判断されます。
それぞれの基準を確認し、自分の状況が該当するかチェックしてみましょう。
雇用保険の加入期間
退職前に、雇用保険に一定期間加入していたことが受給の条件です。
- 自己都合退職:離職日前の2年間に、通算12か月以上の加入
- 会社都合・特定理由離職:離職日前の1年間に、通算6か月以上の加入
勤務先から届く「雇用保険被保険者離職票」の記載内容に注意しましょう。 離職理由や加入期間にミスがあると、支給が遅れたり受給できないこともあります。
就職の意思と求職活動
「就職する意思があること」、そして「実際に求職活動を行っていること」が受給の前提です。
フリーランスとしての独立を考えていても、 「条件に合う求人があれば就職も検討している」という姿勢であれば受給対象となる可能性があります。
ハローワークでは、4週間ごとに求職活動の実績報告が必要になります。
実際の働き方(業務の有無)
退職後すぐにフリーランスとして業務を開始すると、原則として受給できません。
名刺の作成やメールアドレスの取得、業務内容の調査など、収益が発生しない準備にとどめておく必要があります。
一方で、収入が発生する活動(アルバイト・業務委託など)を行った場合は、以下のような扱いになります:
- 1日4時間以上:その日の手当は不支給
- 4時間未満:金額により減額または報告義務が発生
- 報告しないと不正受給とみなされるリスクあり
「働いたつもりがない」場合でも、時間や金銭のやり取りがあれば必ず申告しましょう。
これら3つの条件を満たしていれば、フリーランスとしての独立準備中でも失業手当を受け取れる可能性があります。
では実際に、どのような手続きで受給が始まるのかを見ていきましょう。
申請から受給までの流れと必要な手続き

退職後に失業手当を受け取るには、ハローワークでの申請と認定を段階的に進める必要があります。 以下の流れを押さえて、スムーズに準備を進めましょう。
離職票の受け取りと確認
まずは勤務先から届く「雇用保険被保険者離職票(1・2)」の内容を確認します。 特に「離職理由」や「賃金支払状況」に記載ミスがあると、受給額や開始時期に影響するため要注意です。
ハローワークでの求職申込み
住民票のある地域を管轄するハローワークで求職申込みを行い、離職票を提出します。 なお、申込みはハローワークインターネットサービスから事前にオンラインで行うことも可能です。
雇用保険説明会への参加
申込みの1〜2週間後に雇用保険説明会が実施されます。制度の概要や手続きの説明を受け、以下の書類が交付されます。
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- 初回認定日の案内
💡 この説明会に参加するだけで、1回分の求職活動実績としてカウントされます。
失業認定と求職活動の継続
以降は4週間ごとに「失業認定日」が設けられ、求職活動の実績を報告します。 原則として、各認定期間に2回以上の活動が必要です。
主な活動例:
- セミナーや職業説明会への参加
- 転職サイトの利用・求人検索
- 求人への応募(書類提出や面接)
- ハローワークでの職業相談
このように、退職後に失業手当を受け取るには、ハローワークでの段階的な手続きが欠かせません。
続いて、受給中に気をつけるべき「やっていいこと・ダメなこと」を整理します。
正しく理解すれば、失業手当を安心して活用しながら準備を進められます。
受給中にやっていいこと・ダメなこと

失業手当を受けながら開業準備を進める場合、最も注意したいのは「就職した」とみなされないことです。 収入の有無だけでなく、行動内容によっても判断されるため、制度上の制限を理解しておく必要があります。
収益が発生しない準備はOK
以下のような活動は、原則として就業状態とみなされず、受給を継続できます。
- 名刺や業務用メールアドレスの作成
- 自己紹介用プロフィール資料の整備
- 契約書のひな型作成や条件整理
- 業務に関する情報収集(薬局の比較など)
- 保険やサービスの検討
🔸 ポイントは、「収益が発生しない範囲」「営業活動ではないこと」です。実務上は、こちらから申告しない限り判断されにくい部分でもあります。(仮に後で指摘されても影響は限定的な場合が多い)
開業届の提出はNG
税務署に「開業届」を提出した時点で、原則として失業状態ではなくなります。 そのため、失業手当の支給は終了します。
ただし、所定の条件を満たす場合は「再就職手当」を受け取れる可能性があります(詳しくは次のセクションで解説します)。
短時間の作業も申告が必要
繰り返しになりますが、副業やアルバイト、業務委託などの作業を行った場合、たとえ数時間でも申告が必要です。(申告を怠ると、支給停止や返還など重大な不利益につながります)
作業の長さや収入の多寡によって、扱いは次のように変わります:
- 1日4時間以上:その日の給付は不支給
- 4時間未満:収入に応じて減額または報告義務が発生
- 無報酬の作業:内容によっては「就労」とみなされる可能性あり
申告漏れは不正受給とされ、給付の取り消し・返還・追徴金の対象になります。 「働いたつもりがない」場合でも、時間や金銭のやり取りがあれば必ず申告しましょう。
このように、受給中はやっていい準備・やってはいけない行動を明確に区別することが大切です。 続いて、フリーランスとして開業を進める際に活用できる制度上の選択肢を見ていきましょう。
開業と失業手当の両立策(制度活用編)

フリーランス薬剤師として独立しても、制度を正しく使えば 開業前後のリスクを抑えられます。状況に応じて選びましょう。
準備が整ってから開業するなら|再就職手当を活用する
退職後に準備してから開業したい人向けの選択肢です。 所定の条件を満たし、早期に就職・開業した場合は 残り給付日数に応じた一時金が支給されます。
- 対象:失業手当の受給資格がある状態で本格稼働を開始
- 待機:7日間の待機期間が終了している
- 残日数:所定給付日数の3分の1以上が残っている
- 申告:開業前にハローワークへ事前申告している
- 継続性:1年以上の継続見込みがある業務である
独立初期の資金不安を抑えられるのが利点です。一方で、開業を遅らせる必要がある点には注意しましょう。 詳細は厚生労働省の就職促進給付ページを参照してください。
退職後すぐに専念できるなら|受給期間延長の特例を利用
退職後にすぐ事業に専念できる人向けの選択肢です。 開業期間を受給期間に含めない扱いにし、 将来の受給権を温存できます(最長3年)。
- 対象:離職後に開始した事業である
- 継続:事業が30日以上継続している
- 排他:就業手当・再就職手当は受けていない
- 期限:開業日から2か月以内に申請する
一度開業し、その後に廃業して再就職を考え直す場合でも、受給権を失わずに再開できる可能性があります。 (筆者はありがたいことに勤め先に雇用契約から業務委託契約に切り替える対応を認めてもらえたため、こちらを選びました。)
このように、制度の使い分けで
「準備期間の生活を支えつつ開業につなげる」か
「将来の受給権を守る」かを選べます。
自分が退職後すぐに取引先があるのか、まだ準備段階なのかに応じて、最適な制度を選びましょう。
まとめ|制度を理解して、不安なく独立へ進もう

退職後にフリーランス薬剤師として独立を目指す方にとって、
失業手当をどう使えるかは大きな安心材料になります。
ポイントは3つです:
- ✅ 「就職の意思」と「求職活動」を継続していること
- ✅ 受給中は収益のない準備にとどめ、正直に申告すること
- ✅ 状況に応じて再就職手当や受給期間延長の制度を使い分けること
これらを押さえておけば、制度の範囲内で失業手当を受けながら開業準備を進めることができます。
大切なのは、焦らず段階的に準備を進め、自分の状況に合った制度を選ぶことです。
制度を正しく理解すれば、退職後も不安に振り回されず、独立への一歩を安心して踏み出せます。
✅ 次に進めるアクションはこちら:
オンライン求職登録や窓口での手続きをスムーズにするための事前登録は、公式サイトからも行えます。
👉 ハローワークインターネットサービス(厚生労働省公式|求職申込み・求人検索はこちら)
退職後に必要な他の制度や手続きについても、以下の記事でまとめていますので、あわせてチェックしてみてください。
👉 フリーランス薬剤師の退職後手続きまとめ|健康保険・年金・税金の対応をまとめて解説
あわせて読みたい関連記事:
制度ごとの詳しい解説はこちらの記事でまとめています

