退職してフリーランスとして働き始めるとき、
「健康保険はどうする?」「年金は切り替えが必要?」「失業手当はもらえる?」
と、社会保険まわりの不安が一気に押し寄せてくる方は少なくありません。
薬剤師は日常業務で制度の“名前”には触れていても、
いざ自分が手続きをする段階になると、
「具体的にどう動けばいいのか分からない」 という人も多いです。
調剤薬局では保険証の種類に触れる程度ですし、
病院勤務の場合は社会保険や税金の仕組みを理解しないまま退職を迎える人も珍しくないです。
私自身も、独立を意識してお金の勉強をしていたこともあり、
退職後に必要な手続きの種類は“なんとなく”知っていました。
それでも実際に退職してみると、制度選択や期限調整など思った以上にやることが多く、
「知っているつもり」と「やってみる」は別物だと痛感しました。
本記事では、フリーランス薬剤師が退職後すぐに対応すべき
健康保険・年金・失業手当の手続きを、要点に絞って整理します。
あわせて、住民税・退職金・確定申告など、
退職直後にどこまで気にしておけば十分なのかを把握できる構成にしています。
読み終える頃には、
- 退職直後に何を優先して進めればいいか
- 健康保険・年金・失業手当の判断ポイント
- 税金まわりで押さえるべき最低限の項目
がスッと整理され、独立準備を迷わず進められるはずです。
退職後の手続きは不安がつきものですが、
ポイントさえ押さえれば、決して難しくありません。
ここから一緒に、フリーランスとしての土台を整えていきましょう。
退職までの流れを確認したい方はこちら。
👉 退職準備とスケジュールの立て方|独立を見据える薬剤師の退職ガイド
また、「最初の案件づくり」が気になる方はこちらもどうぞ。
👉 フリーランス薬剤師の初案件の作り方は?|雇用から業務委託への実体験
まずはここから:退職直後に確認したいこと

退職後の手続きは、「まず何から手をつければいいのか」が分かりにくいものです。
ここでは、健康保険・年金・失業手当の詳細に進む前に、退職直後に押さえておきたい“全体の土台”を簡潔に整理します。
まず確認しておきたいのが、退職日と社会保険の資格喪失タイミングです。
- 健康保険
退職日の翌日から使えなくなります。
任意継続・薬剤師国保・市町村国保のどれを選ぶかを、早めに検討する必要があります。 - 年金
退職日の翌日から、厚生年金から国民年金へ切り替わります。 - 雇用保険
退職と同時に被保険者資格を喪失します。
失業手当を検討する場合は、このあと条件や手続きの確認が必要になります。
なお、申請には離職票が必要で、手元に届くまで1〜3週間かかることもあります。
いずれの制度も、退職日を起点に手続きが進みます。
まずは全体の流れとスケジュール感を押さえておきましょう。
退職後すぐに手続きする必要はありませんが、税金まわりの扱いが変わる点だけは事前に知っておくと安心です。
特に次の2つは必ず押さえておきたいポイントです。
- 住民税はまとめて支払うことになる
- 確定申告が必要になる
特に次の2点は、事前に知っておくだけでも安心です。
このあと解説する健康保険・年金・失業手当・税金の各パートは、
すべてこの流れに沿って整理しています。
健康保険の選び方|任意継続・薬剤師国保・市町村国保の基本

退職すると会社の健康保険の資格がなくなるため、フリーランスとして新しい健康保険に加入する必要があります。
ここでは、退職直後に押さえておきたい「資格喪失のタイミング」と「主な選択肢」のみを簡潔に整理します。
資格喪失と加入期限(20日以内)
会社の健康保険は退職日の翌日に資格喪失となります。
そのため、次の保険を早めに決めておくことが大切です。
特に注意したいのが、任意継続の申請期限が「退職後20日以内」であること。
この期限を過ぎると選べなくなるため、まず最初に検討する制度になります。
薬剤師国保や市町村国保に加入する場合は、
原則として資格喪失日以降の加入となります。
自治体によっては資格喪失前から事前手続きができる場合もあるため、
事前に確認しておくとスムーズです。
健康保険は、手続き後に遡って適用されます。
ただし、一時的に保険証が手元にない期間が生じることもあるため、
退職後は、なるべく空白期間ができないよう早めに手続きを進めておくと安心です。
主な選択肢と特徴(任意継続・薬剤師国保・市区町村国保)
健康保険の選択肢は主に次の3つです。
任意継続(任意継続被保険者制度)
会社員時代に加入していた健康保険を、最長2年間継続できる制度です。
- 保険料:全額自己負担(標準報酬月額に上限あり)
- 加入条件:
退職日までに継続して2か月以上被保険者であったこと
退職日の翌日から20日以内に申請すること
薬剤師国保(薬剤師国民健康保険組合)
薬剤師向けの国民健康保険組合で、独立直後の比較対象になることが多い制度です。
- 保険料:原則定額(地域によって所得比例となる場合あり)
- 加入条件:組合による(地域差が大きいので要確認)
市区町村の国民健康保険
住民票のある市区町村で加入する最も一般的な国保です。
- 保険料:所得比例
- 加入条件:資格喪失後、住民票のある市区町村で手続きすること
選び方の流れ(判断のポイント)
健康保険は、次の順番で比較すると迷わず進められます。
- 期限が最も早い「任意継続」を試算する
20日以内に申請が必要なため、まず保険料を試算します。 - 薬剤師国保に加入できるか確認する
地域差が大きいため、加入条件と保険料を必ずチェックします。 - 市町村国保と比較し、負担の見通しを立てる
会社員時代の所得が低い場合は、市町村国保の方が安くなることもあります。
どの制度が最適かは、「保険料」「加入条件」によって変わります。
✅ 筆者のケース:
筆者の場合、退職前に協会けんぽの保険料を試算したところ、標準報酬月額が上限に達していたため任意継続が最も割安でした。
そのため、期限内(退職後20日以内)に任意継続の手続きをしました。
👉 詳しく知りたい方はこちら:
健康保険制度の比較や、保険料試算のポイントを詳しく解説しています。
退職+フリーランス初年度の健康保険ガイド|薬剤師国保・任意継続を徹底比較
年金の切り替え|厚生年金から国民年金へ
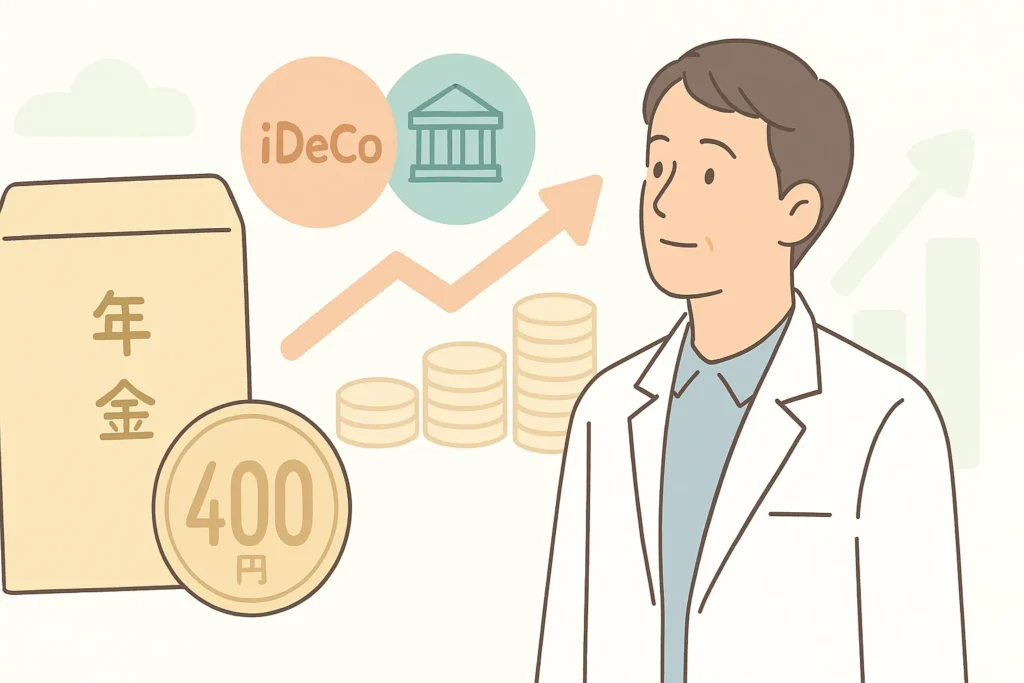
退職すると厚生年金の資格がなくなるため、国民年金(1号被保険者)への切り替えが必要になります。健康保険と同じく、退職後すぐに行う優先度の高い手続きです。
切り替え手続き(14日以内)
厚生年金の資格は退職日の翌日に喪失します。
そのため、退職後14日以内に、住民票のある市区町村で国民年金への切り替え手続きを行います。
手続き方法は次のいずれかです。
- 市区町村の窓口で手続き
- マイナポータル(オンライン)で申請
必要書類は、退職日が確認できる書類(退職証明書など)と本人確認書類です。
離職票の到着を待つ必要はないため、先に年金手続きを進めて問題ありません。
保険料・免除・猶予制度の基本
国民年金は、毎月定額の保険料を納める仕組みです。(前納も可)
収入状況に応じて保険料の負担を軽くできる免除・猶予制度も用意されています。
ただし、退職初年度は前年の給与所得で判定されるため、
通常の免除・猶予制度の対象になりにくい点に注意が必要です。
(※退職(失業)による特例免除という制度もありますが、ここでは割愛します。)
翌年度以降は、フリーランスの所得が下がれば、
通常の免除・猶予制度が適用できるケースもあります。
まずは制度の仕組みを知っておくだけで十分です。
付加年金・iDeCoなどの上乗せ制度
将来の年金に不安がある方は、次の上乗せ制度も検討できます。
- 付加年金:
月400円の追加で、受給時に200円 × 納付月数が上乗せ
→ 2年で元が取れる仕組み - iDeCo:
すでに利用している場合は、退職後に区分変更が必要(2号 → 1号)
これから始める場合も、1号被保険者として加入できます。
→ 節税しながら老後資金を積み立てたい人に向いています。
どちらも加入は必須ではありませんが、独立後の年金対策として知っておくと選択肢が広がります。
✅ 筆者のケース:
筆者の場合、退職後すぐにマイナポータルから国民年金への切り替え手続きを行いました。
あわせて、将来の受給額を少しでも増やすために付加年金を同時に申し込み、
その後、利用中だった iDeCo の区分変更(2号→1号)を証券会社で手続きしています。
👉 詳しく知りたい方はこちら:
年金の切り替え手続き、免除・猶予制度、付加年金やiDeCoの扱いを詳しく解説しています。
退職+フリーランス初年度の年金手続きガイド|切り替え・免除・iDeCoも解説
失業手当の扱い|独立予定でも申請できるケース

退職後にフリーランスとして独立を予定していても、条件を満たせば失業手当(基本手当)を受け取れる可能性があります。
ただし、失業手当は「就職しようと思えば働ける状態」が前提のため、動き出すタイミングとの調整が必要です。
まずは基本ルールを整理します。
失業手当の基本条件
失業手当を受け取るには、次の2つが必須です。
- 就職する意思があること
- 就職できる能力があること
そのうえで、離職前の雇用保険加入期間が次を満たしている必要があります。
- 自己都合退職:過去2年に通算12か月以上
- 会社都合退職:過去1年に通算6か月以上
この条件を満たしていれば、ハローワークで離職票の提出・求職申込みを行うことで受給手続きに進めます。
給付制限の基本
退職後はまず7日間の待機期間があります。
その後の給付開始時期は次のとおりです。
- 自己都合退職:1か月の給付制限
- 会社都合退職:給付制限なし(待機後すぐ受給)
なお、退職後すぐに業務委託で働き始める場合は、実態として「就労」と判断されるため 失業手当は受給できません。
ただし、失業手当の受給資格そのものは残るため、後述する特例を利用できます。
受給期間延長(最大3年)
病気・出産・家族の介護など、求職活動ができない事情がある場合は、
退職後2か月以内の申請で受給開始を最大3年まで延長できます。
退職後すぐに薬局と業務委託契約を結び、当面は事業に専念する場合も
この制度の対象となります。
この特例を利用して
- 当面は受給せずに働く
- 受給資格だけは残しておく
という状態にしておくのが合理的です。
独立予定(業務委託開始)との関係
以上を踏まえると、独立を予定している場合に取り得る選択肢は2つに整理できます。
▼ 退職後すぐに業務委託で働く場合
→ 受給期間延長を申請する(退職後2か月以内)
開業するため今すぐに受給の必要はありませんが、
受給資格だけ確保しておくことで後から必要に応じて受け取れるようになります。
▼ 退職後しばらく開業準備を進める場合
→ 失業手当の受給を検討
退職後しばらく仕事をしない期間を設ける場合は、
状況によっては失業手当を受給できる場合があります。
開業準備の進み具合や働ける状況は人によって異なりますが、
独立を前提にしていても、制度上は「求職活動が可能な状態」であることが求められます。
そのため、ハローワークでは、
現在の状況を丁寧に伝えつつ、再就職の可能性も含めて検討している旨を示すとスムーズです。
✅ 筆者のケース:
筆者は退職後すぐに業務委託契約で働き始める予定だったため、失業手当の受給は対象外でした。
その一方で、後から受け取れる選択肢を残すために受給期間延長の申請を退職後2か月以内に行っています。
👉 詳しく知りたい方はこちら:
失業手当の受給条件、伝え方、独立時の注意点を詳しく解説しています。
退職+フリーランス初年度の失業手当ガイド|受給条件・伝え方・注意点をわかりやすく解説
税金の扱い|退職後に押さえるポイント

退職後は、勤務先での年末調整が使えなくなるため、
税金の扱いも一度整理し直す必要があります。
とはいえ、退職直後にすべてを理解する必要はありません。
この段階で押さえておきたいポイントは、大きく3つだけです。
住民税(退職時期で支払い方法が変わる)
住民税は前年の所得に対して課税される税金のため、
退職しても必ず支払いが発生します。
ただし、退職した時期によって支払い方法が変わります。
- 1〜5月に退職した場合
残りの住民税が、退職時の給与や退職金から一括で天引きされます。 - 6〜12月に退職した場合
市区町村から納付書が届き、自分で納付します。
支払いは年4回の分割払い(6月・8月・10月・翌年1月)が基本ですが、
納付書がまとめて届くため、一括払いも可能です。
なお、クレジットカードやQRコード決済(PayPayなど)といった
キャッシュレス納付に対応している自治体もありますが、
利用できる支払い方法は地域によって異なるため、事前に確認が必要です。
支払う住民税の総額が増えるわけではありませんが、
1回あたりの支払額が大きくなるため、負担が増えたように感じやすい点には注意が必要です。
あらかじめ負担感を把握しておくと安心です。
(例:前年所得が約500万円の場合、住民税は年間およそ24万〜25万円)
フリーランス初年度は収入が不安定になりやすいため、
住民税の納付時期とおおよその金額を早めに把握しておくと、
資金繰りの見通しが立てやすくなります。
退職金(申告書の提出で確定申告不要)
退職金を受け取る際に退職所得申告書を提出しておけば、
原則として確定申告は不要です(源泉徴収で完結します)。
勤務先が中退共(中小企業退職金共済)に加入している場合は、
退職後に自分で請求手続きを行う点だけ注意が必要です。
中退共の場合の一般的な流れは次のとおりです。
- 退職時に、会社から「退職金共済手帳」(3枚つづりの書類)を受け取る
- 3枚目の「退職金請求書」に必要事項を記入し、郵送する
※この請求書の中に退職所得申告書の記載欄があるため、
あわせて記入すれば、原則として確定申告は不要です。 - 数週間後、指定口座に退職金が振り込まれる
書類の記入と郵送だけで完了するため、複雑な手続きはありません。
もし退職所得申告書を提出していない場合は、
税率が高く源泉徴収されてしまいますが、
後から確定申告で精算し、払い過ぎた税金を取り戻すことができます。
所得税(確定申告が必要な主なケース)
退職した年の所得税は、勤務先で年末調整が行われないため、
自分で確定申告を行う必要があります。
主に次のようなケースでは、確定申告が必要です。
- 退職前に年末調整を受けていない場合
→ 源泉徴収票をもとに、1年分の所得税を自分で精算します - 給与以外の所得がある場合
(フリーランスの事業所得・アルバイト収入など) - 医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税)など、控除を受けたい場合
フリーランス初年度は、
退職金・給与・事業所得が混在しやすいため、
所得区分ごとの扱いを早めに整理しておくと確定申告がスムーズです。
✅ 筆者のケース:
筆者の場合、6月30日退職だったため、
翌月以降の住民税は納付書による普通徴収となりました。
支払い期限まで紙の納付書を保管するのが面倒だったため、
QRコード決済(PayPay)を使って一括で納付しています。
退職金は中退共に加入していたため、自分で請求手続きを行い、
申請からおよそ3週間ほどで振り込みを受けました。
給与所得と事業所得は、翌年の確定申告でまとめて申告しています。
まとめ|まず流れを把握すれば、退職後の手続きはスムーズに

退職後の手続きは、ひとつずつ見ていくと複雑に感じがちですが、
健康保険 → 年金 → 雇用保険 の順に整理すると迷いにくくなります。
どれも「退職日」を起点に動く手続きですが、
特に期限が短いのは健康保険と年金の切り替えです。
まずこの2つを済ませるだけでも、退職直後の不安はぐっと減ります。
一方で、フリーランス初年度は
退職金・住民税・事業所得などが重なり、
税金まわりの扱いがいつもより複雑になりやすい時期でもあります。
とはいえ、全体の流れを早めに把握しておけば、
必要以上に慌てず、落ち着いて対応できます。
退職後の制度は、細かく覚えるよりも
「流れ」で理解する方が圧倒的にラクです。
ここまで整理できていれば、土台はすでに整っています。
余力があれば、次のステップとして
フリーランスとしての働き方を形にする準備に進んでいきましょう。
✅ 次に進めるアクションはこちら:
👉 フリーランス薬剤師の開業届と青色申告|退職前後でも迷わず進める方法
開業準備の最初に取り組む「開業届・青色申告承認申請」の具体的な進め方を画像付きで解説。
👉 フリーランス薬剤師の開業準備まとめ|独立前に必要な実務と手続きをまとめて確認
退職後の手続きから開業準備の流れまで、一度で俯瞰できます。




